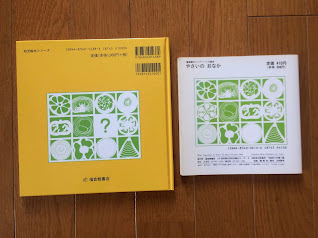人に伝えたいことやものが生じたとき、ぼくはその思いを絵本という形にします。その思いをどう表現すれば多くの人に伝わるのか、いつも考えています。完成した絵本が人の手に渡ったとき、その絵本は読者のものになります。その絵本を見た読者は、何を感じどう解釈するか人様々です。作者の思いとは別のことを感じたり、作者が思いもよらない発見をするかも知れません。1つのものがプラスに広がっていくことは、作者にとっても大きな喜びです。でもマイナスに広がっていくこともあります。それは作者にとって悲しいことです。
大人が選んだ絵本をどのように子供に読み聞かせているのか、また絵本を見て子供や大人はどんな印象を受けているのか、読者からお便りを頂かない限り絵本の作者は知る由もありませんでした。ところが、今は違います。だれもがインターネットでブログやHPを作り自分の考えや意見を発信するようになり、自分の好きな絵本や子供の感想、評価や宣伝までもする状況になっています。自分が描いた絵本を検索すると、様々な意見や感想を知ることができます。そんな中には思いもよらなかった感想があり、驚いたり嬉しかったり悲しかったりもします。あまり多く読者の声を聞き過ぎると、鬱になってしまいそうなので時々見て参考にしています。
近ごろは若いお父さんも子育てに加わって、絵本の読み聞かせをしているお父さんが増えました。また図書館でも読み聞かせのボランティアグループも増えているようです。ぼくも幼稚園で10年以上絵本の読み聞かせをしてきたので、みなさんがどのようにやっているのか気になっていました。そこで「やさいのおなか」の読み聞かせを調べたところ意外なことがわかりました。
「やさいのおなか」は日本全国たくさんのボランティアグループによって読み聞かせの絵本として使って頂いています。作者としても嬉しい限りです。ただ気になる点が一つあります。それは、クイズのように子供達に問題を見せて答えを言わせる方法で読み聞かせをしているとき、子供から返ってきた答えに読み手がどう反応しているかと言う点です。タイトルが「やさい」となっているので、野菜以外の答えが子供から返ってきたときに、その答えを簡単に否定してしまう人がいます。それは作者の意図とは全く違いマイナスな読み方です。
この絵本が生まれた時にも多くの読者からお手紙を頂きました。多くの感想は、やさいの断面を見て野菜以外のものを想像した答えが子供達からたくさん返ったことに親や先生は驚き、柔軟で豊かな子供達の創造力を再認識したこと。そして、子供達だけではなく大人も創造性を広げ身近な発見をさせてくれた絵本だとほめて頂きました。この時はまだ大人にも考える余裕があったのかもしれません。答えは1つだと決めつけた石頭ではなく、柔軟な遊び心をもった大人や子供達がたくさんいたのでしょうか?
「やさいのせなか」を出版したあと、あれは子供には難しすぎるという大人の意見をネットでたくさん見つけました。確かにクイズ絵本として読み聞かせて、1つの答えだけを見いだそうとすれば、誰にとっても難しい問題になると思います。作者としてはそんなことを望んで絵本を作ったのではもちろんありません。
「くだものなんだ」は「やさいのおなか」の果物偏です。でも絵本を作りながら、タイトルや文をどうするか悩みました。23年前に「やさいのおなか」を作ったときは、文にヒントや作者のイメージを書くことをしませんでした。それは読者にとってよけいなおせっかいだと考えたからです。しかし、今回は敢えてよけいなおせっかいをすることにしました。その理由は上記の通りマイナスな読み聞かせが広がっていると感じたからです。
「くだものなんだ」というタイトルには2つの意味があります。質問するように「くだもの なーんだ?」と読むこともできますし、「くだもの だったんだ!」という認識することもできます。どうとらえるかは読者におまかせします。果物の細密描写は水彩絵の具で描きました。果物には同じ種類でもたくさんの品種があり形もそれぞれ違います。ここに描かれた果物は、全て石垣島で売られているものの中から選びました。果物に詳しい人ならその品種もわかるかも知れません。果物の断面図は、とてもユニークな形をしています。シルエットで見ると様々な形のものを想像することができます。果物だということを忘れさせるほど不思議な形をしています。「やさいのおなか」のときは「これ なあに」と質問だけでしたが、今回は果物以外のイメージをふくらませてほしいと思いぼくのイメージを付け加えました。もちろん他のものにも見えるので、何に見えるか自分のイメージを大切にして楽しんで頂きたいと思っています。
最初に書いたように、絵本は読者が選んだとき読者のものとなります。絵本という素材をどう料理するかはあなた次第です。どうか子供達が元気になりあなたも子供達からたくさんのことを学べるよう料理してください。